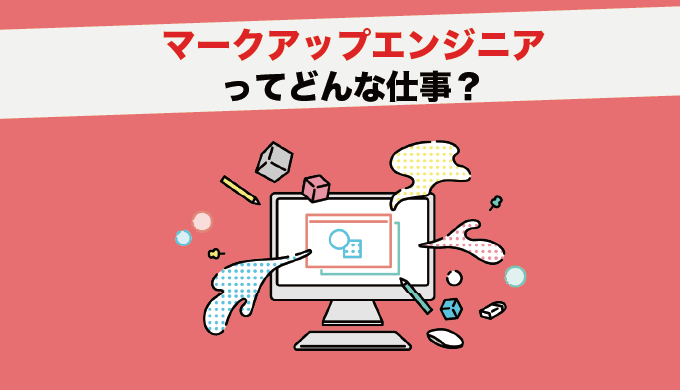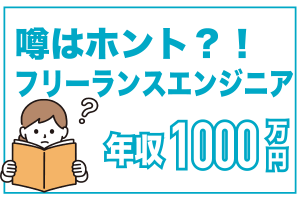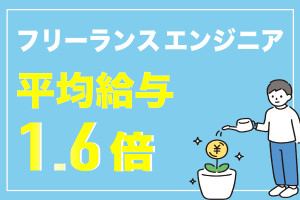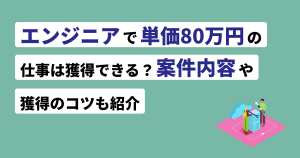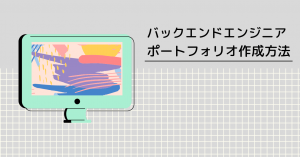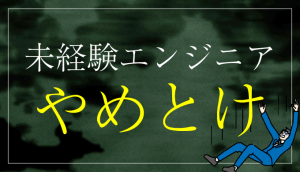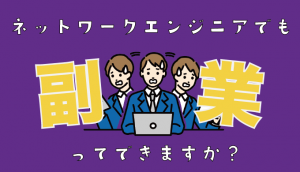マークアップエンジニアはWebサイト制作にかかせない存在です。
スマートフォンやタブレットの普及で誰もがインターネットに気軽にアクセスできる影響もあり、マークアップエンジニアの需要は年々増えています。
そんなマークアップエンジニアに興味を持っても
「マークアップエンジニアはどんな仕事をするの?」
「マークアップエンジニアと他のエンジニアとの違いは?」
「未経験からマークアップエンジニアになる具体的な方法はあるの?」
など疑問に思っているでしょう。
マークアップエンジニアに転職したい人でも、年収や取るべき資格、具体的な仕事内容などマークアップエンジニアを目指す前に、詳しい内容を知りたい人もいるはず。
そこで今回は、マークアップエンジニアの年収や仕事内容などについて徹底的に解説します。
この記事を読めば、未経験から目指すSTEPや転職方法までマークアップエンジニアについて深く理解できますよ。
マークアップエンジニアとは?
結論、マークアップエンジニアは「マークアップ言語の知識を持ち、それを活用して問題を解決する人たち」のことです。
そもそもマークアップエンジニアという言葉は、文章の構造やレイアウトを表現することを意味する「Markup(マークアップ)」と、「技術者」の意味を持つ英単語「Engineer(エンジニア)」が元になっているんですね。
コンピューターが文章を解釈しようとした場合、どの部分が見出しでどの部分が本文なのか、どの部分を強調させたいかなどを判別するために用います。
マークアップを表現するための言語を「マークアップ言語」といい、HTMLやXMLなどさまざまな種類があります。
マークアップ言語は、あくまで文章構造を表現するための言語であり、プログラムを動かすための言語ではありません。
そのため、マークアップ言語はプログラミング言語とは異なるため注意してください。
さまざまな種類があるマークアップ言語ですが、この場合はHTMLが適切です。
つまり、マークアップエンジニアは「HTMLを利用して、Webサイトを作成する人たち」という意味になります。
マークアップエンジニアの仕事内容
次にマークアップエンジニアの詳しい仕事内容についてみてみましょう。
会社によって細かい違いがありますが、仕事は大きく分けて4つあります。
- コーディング
- バグの修正
- CMSの構築・設計
- SEO対策
それぞれ詳しく解説しますね。
コーディング
コーディングとは、Webサイトをデザイン通りに表示させるようにプログラミングする作業です。
現場では、実際にデザイナーが作ったデザイン通りに忠実に再現します。
使うプログラミング言語はHTML5とCSSです。
コーディング作業は自分1人で行うものではなく、チームで作成します。
チーム全員がわかるように誰がみてもわかりやすいコードを書くスキルが求められます。
また、期日もあるので、正確にプログラミングするスキルも重要も必要です。
バグの修正
バグとは不具合のことです。コードに不具合があると、サイトが表示されないことやサイトの画像が抜け落ちてしまうこともあります。
マークアップエンジニアはバグを修正し、サイトやユーザーに対してアップデートという形で修正した内容を常に表示・提供しているのです。
例えば、音楽配信アプリやスマホゲームでは定期的にアップデートが行われていますよね。
これらもバグが見つかれば、マークアップエンジニアが修正し、アップデートしたバージョンを公開します。
私たちがWebサイトやアプリを楽しめるのは、マークアップエンジニアが日々バグを修正してくれているからなんですね。
CMSの構築・設計
CMSとは、簡単に説明するとWebページの編集を簡単・便利に行えるソフトウェアです。
CMSを導入するメリットは、専門知識なくてもWebページの更新や新規作成、導入した会社の予算削減できるメリットがあります。
デメリットはCMSを導入していないとプログラミングの知識を持っている人が必要になり、Webサイトも1つずつ作ることになり、多く時間がかかるのです。
CMSを導入した会社は、新しくWebページが必要になったときでもプログラミングの専門知識なしに新規Webページを自動生成します。
誰でも管理できることやWebページが作成できることから最近導入をしている会社が増えているんですね。
マークアップエンジニアは、そのCMSの構築・設計を担当をしています。
SEO対策
最後にSEO対策です。Webページを多くの人に見てもらうときは、検索順位を上げて行かないといけません。
検索順位を上げることで、人の目に入りやすくなり多くの人が訪れます。
マークアップエンジニアはSEO対策も担当しており、検索上位に表示させるための工夫をするのです。
しかし、SEOの評価基準は頻繁に変わるので、常に情報収集しておく必要があります。
SEOの評価基準は自分1人で理解するにはとても大変なので、SNSを使って調べましょう。
マークアップエンジニアの平均年収
| 年齢 | 年収 |
|---|---|
| 20代 | 250万円〜350万円 |
| 30代 | 350万円〜500万円 |
| 40代 | 600万円〜650万円 |
マークアップエンジニア(フロントエンドエンジニア)の年収は、20代で250万~350万、30代では350万~500万、40代では600万~650万程度です。
ただし、スキルの程度によっては年収1,000万を超える場合もあります。
※平均年収のデータは、マイナビエージェント と 求人ボックスの情報を基にしています。
マークアップエンジニアに必要な言語
マークアップエンジニアに必要な言語は、マークアップ言語のみではありません。
スタイルシート言語であるCSSや、プログラミング言語の中でもJanaScriptの習得が必要になるんですね。
会社や企業によってマークアップエンジニアの役割は多少異なりますが、一般的にWebサイト画面の制作全般を担うことになります。
最近では、動画サービスの制作も多いことから動的な機能を付与するJavaScriptに関する知識やスキルも大切なんですね。
現場で活躍するマークアップエンジニアであれば、HTML・CSS・JavaScriptは習得すべき必須の言語と言えます。
それぞれの言語が、作業において相互に作用するので並行して学んでいくのがおすすめですよ。
マークアップエンジニアに必要なスキル
マークアップエンジニアを目指そうか考えている人の中には、必要なスキルが気になる!という方もいるでしょう。
主に、マークアップエンジニアに必要なスキルとして、
- Webサイトの制作スキル
- ライブラリ・フレームワークを扱う技術力
- コミュニケーションスキル
上記3つのスキルが挙げられます。
まず、マークアップエンジニア必須スキルの1つ目は、Webサイト作成に関わる複数の言語知識です。
HTMLのようなマークアップ言語だけでなく、CSSやJavaScriptを理解しておけば、仕事がなくなる心配はありません。
また、ライブラリ・フレームワークの知識もマークアップエンジニア必須スキルの1つです。
短期間でWebサイトが作成できるだけでなく、メンテナンスも楽にできることから、今日のWebサイト作成ではライブラリとフレームワークを利用するのが一般的となっています。
Webデザイナーとのコミュニケーションが欠かせないマークアップエンジニアにとって、コミュニケーションスキルは必須です。
大規模なWebサイト制作の際は、複数のマークアップエンジニアと情報共有しながら仕事を分担します。
仕事を円滑に進行させるためにも、周囲の人とコミュニケーションをとることを怠ってはいけません。
マークアップエンジニアにおすすめな資格
マークアップエンジニアは、資格を取得していなくてもなれる職業です。
しかし、Web開発に関する資格を受験すれば、勉強した知識を仕事で活用できます。
そこで、マークアップエンジニアにおすすめな資格を3つ紹介していきます。
おすすめの資格として、
- Webクリエイター能力検定試験
- HTML5プロフェッショナル認定試験
- 基本情報技術者
上記3つが挙げられます。
Webクリエイター能力検定試験とHTML5プロフェッショナル認定試験は、段階に応じて試験のレベルが分かれています。
どちらも、マークアップエンジニアに大切なHTMLに関する知識やスキルにつながる内容になっていますよ。
また、IT技術に関する国家資格の一つで、IT技術の基本知識を有して実践利用できる人が対象です。
上記2つの資格と比べて、Webに限らずIT技術に関する分野から幅広く問題が出題されるので注意してくださいね。
マークアップエンジニアとその他のエンジニアの違い
マークアップエンジニアは、エンジニアの中でもWeb画面の制作に特化した職種です。
主にWebコンテンツの市場で活躍することが多いと言えるでしょう。
また、マークアップエンジニアは他のエンジニアと協力して仕事を進めていくことも多々あります。
それぞれのエンジニアに仕事の特徴があり、活躍する市場も変わってくるんですね。
ITエンジニアを目指す方の中には、どのエンジニア職種を目指せば良いのか迷っている方もいるでしょう。
そこで、マークアップエンジニアと他のエンジニアの違いについて紹介していきます。
同じITエンジニアの中でも、あなたに合った職種が見つかる可能性もあるので参考にしてみてください。
マークアップエンジニアとコーダーの違い
マークアップエンジニアはWebサイトを制作する職種なので、コーダーと同様の職種と考えている人も多いでしょう。
ただ、それぞれの職種は役割が異なるんですね。
そもそもコーダーは、デザイナーの指示に沿ってコーディングをしていきます。
コーディングの際には、アレンジを加えず指示書を守って忠実にコーディングすることが求められるんですね。
コーダーはHTMLやCSSを組み立てていく過程でJavaScriptなどを用いることは少なく、HTML・CSSで完結できる部分を担当する場合がほとんどです。
オリジナリティや自分の意見を制作に持ち込むことはあまりないんです。
逆にマークアップエンジニアは、デザイナーの指示どおりにWebサイトを作るわけではありません。
クライアントに合わせたサイトの目的を正しく理解して、SEO対策なども行ってより良いコンテンツを利用できるように制作を進めていきます。
SEOに限らずUIなどに関する知識も必要なマークアップエンジニアは、一般的にはコーダーよりもスキルが必要と言えるでしょう。
扱えるスキルや知識量が増えていけば、マークアップエンジニアとしての価値も高まっていきますよ。
マークアップエンジニアとフロントエンドエンジニアの違い
フロントエンドエンジニアは、エンジニア職種の中でもマークアップエンジニアと仕事内容が似ているんです。
他にも、Webコーダーがフロントエンドエンジニアやマークアアップエンジニアと似た役割を担っています。
そもそも、フロントエンドエンジニアが登場するまでフロントエンドの仕事を主に任されていたのはマークアップエンジニアでした。
フロントエンドで要求されることが増えてきたことで、専門性に特化したフロントエンドエンジニアという職種が生まれたんですね。
また、フロントエンドエンジニアはマークアップエンジニアやWebコーダーのキャリアアップ後の職種でもあります。
それぞれのエンジニアが、同じ現場で協力して作業することもあるんですね。
また、フロントエンドエンジニアについて詳しく知りたい方は以下の記事でも詳しく紹介しています。参考にしてみてくださいね。
→【徹底解説】フロントエンドエンジニアとは?仕事内容・年収・スキル・将来性まで
マークアップエンジニアとインフラエンジニアの違い
インフラエンジニアは、サーバーエンジニアやネットワークエンジニアなどを含む総称です。
そもそもインフラエンジニアとは、IT業務におけるインフラストラクチャを設計・構築・運用・メンテナンスまで行うエンジニアのことなんですね。
インフラエンジニアは名前の通り、インフラに関わるエンジニアというだけあって仕事内容は幅広いんですね。
ネットワークの構築に関わるのはネットワークエンジニアですし、サーバーに関わるのがサーバーサイドエンジニアになります。
Webコンテンツの市場の中でも、ユーザーに触れる画面などのフロントエンドを担うのがマークアップエンジニアです。
インフラエンジニアは、目に触れないバックエンド全般を担当する真逆の役割なんですね。
サーバーの保守に関わるインフラエンジニアの中には、サーバーに不具合があればすぐに現場に駆けつける必要がある方もいます。
決して簡単な仕事ではありませんが、社会に対する貢献度も高くやりがいのある職種の1つです。
さらにインフラエンジニアについて深く知りたいという方は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね。
→【2022年最新】インフラエンジニアとは?未経験・転職別になる5STEP
マークアップエンジニアとシステムエンジニアの違い
システムエンジニアという言葉は、エンジニア職種の中でもよく耳にするという方も多いでしょう。
ITエンジニアの代表的な職種とも言えるのが、システムエンジニアです。
システムエンジニアは、名前の通りにコンテンツの核となるシステムの設計を担当しています。
システムの設計は大きく分けると基本設計と詳細設計の2つに分けられているんですね。
中でも、主にユーザーの見える部分の仕様を考える基本設計ではそれぞれのエンジニアが関わり合うこともあります。
ユーザーに見えるフロントエンド部分の中でも、画面制作に関わるマークアップエンジニアはWebコンテンツ制作の核となる存在です。
ただ、システムエンジニアはシステム設計の後にプログラムを作成し動作確認まで行います。
システムエンジニアの仕事の中には、精密かつ地道な作業も多いのが特徴です。
さらにシステムエンジニアについて深く知りたいという方は、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてくださいね。
→システムエンジニアとはどんな仕事?年収や資格、将来キャリアパスも紹介
マークアップエンジニアとデータベースエンジニアの違い
データベースエンジニアとは、データベースの開発・設計・管理などを行うエンジニアのことです。
会社や企業の情報システムを支えるのに欠かせないのが、データベースエンジニアなんですね。
ITの活用が当たり前となった現在では、どの会社や企業でもインターネット上でのデータの管理や活用が欠かせなくなりました。
データの活用に欠かせないデータベースは図書館のようなもので、常に整理しておくことで必要なデータをすぐに取り出すことが可能です。
また、データベースエンジニアは担当する業務内容によって以下の3職種に分類されます。
- データベース開発・設計者
- データベース管理者
- データベース運用者
それぞれの業務で扱う知識やスキルは異なりますが、データベースに関わるプロフェッショナルなのがデータベースエンジニアです。
マークアップエンジニアとは、大きく業務内容や必要とされるスキルが変わってくるんですね。
さらにデータベースエンジニアについて知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてくださいね。
→今更聞けない!データベースエンジニアとは?仕事内容や年収、将来性、資格も紹介
マークアップエンジニアの仕事はきつい?やりがいはある?
もし、あなたがこれからマークアップエンジニアになろうか考えているのであれば、
「マークアップエンジニアの仕事に、やりがいはある?」
「実際、きつい仕事なんじゃ…?」
「マークアップエンジニアが、自分のやりたいことなのか考えたい。」
など気になる方もいるでしょう。
人生の幸福度を左右する仕事のやりがいや、つらさは大事な判断材料になります。
そこでここでは、マークアップエンジニアの仕事はきついのか?ややりがいについて解説していきます。
仕事選びに大切なのは、仕事のメリットとデメリットの両方を踏まえて考えることです。
マークアップエンジニアがあなたに合った仕事かどうかチェックしてみてくださいね。
マークアップエンジニアはきつい仕事?
調べてみたところ、マークアップエンジニアはきついと検索している人は一定数いるようです。
ただ、なぜマークアップエンジニアはきつい印象を持たれているのか知りたいですよね。
マークアップエンジニアがきつい仕事だと言われている理由として、
- 給料が低い
- キャリアアップしづらい職種
- CMSの進歩によって、将来性が見込みにくい
などが挙げられます。
実際、ITエンジニア全体の平均年収が500万円前後(2021年6月現在)の中、マークアップエンジニアの平均年収は450万円前後(2021年6月現在)と下回っています。
もちろんスキルや実務経験、会社や企業によって給与は異なるので参考程度に捉えてくださいね。
また、マークアップエンジニアが主に扱うのは画面の表示に関する分野です。
プログラムに関しては専門のエンジニアが担当し、デザインはWebデザイナーと仕事が分担されて周辺の技術を身に付ける機会が少ないこともあるんですね。
さらに、最近ではCMSを使うことで知識のない人でもWebサイトの作成ができるようになりました。
上記の理由を踏まえると、Webデザインに特化しているなどの専門性がないマークアップエンジニアは需要が下がっていく傾向にあります。
マークアップエンジニアのやりがいは?
結論からいうと、マークアップエンジニアはやりがいのある仕事です。
自身の専門スキルを追求して極めていくやりがいや、クライアントにコーディングしたWebサイトを使ってもらい感想を頂けることもあるでしょう。
また、Webサイト制作に関するプログラミング言語やライブラリなど、最先端の知識や技術に触れていたい人にもおすすめです。
常に新しい知識や技術をキャッチアップすることは、あなたのキャリアアップにもつながる可能性があります。
さらにマークアップエンジニアには、SEO対策を踏まえてユーザーが使いやすいWebサイトを制作するスキルが求められます。
だからこそ、SEOに関する分野を追求したいなどの1つのことを極めたい方も向いているでしょう。
マークアップエンジニアは、専門性を追求することも幅広い知識を身につけてマルチに活躍することもできる職種です。
あなたのやりたいことや伸ばしていきたいスキルに沿ったマークアップエンジニアを目指してみてください。
マークアップエンジニアの将来性やキャリアパスは?
先ほど、CMSの台頭もありマークアップエンジニアの需要は下がっていく可能性もあると紹介しました。
ただ、身につけていく知識やスキルの分野によって、キャリアパスや将来性も大きく変わってくるのも事実です。
仕事は、ただお金をもらうだけでなく生活の中でも多くの時間を費やします。
あなたの生活における満足度を左右する大切な要素だからこそ、将来性や今後のキャリアパスは確認しておきたいですよね。
そこで、マークアップエンジニアのキャリアパスや将来性について詳しく紹介していきます。
マークアップエンジニアの先のキャリアまで見据えていきたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
マークアップエンジニアに将来性はある?
IT技術の進歩や発達が急速に進む現在では、どのような仕事であっても将来性が必ずあるとは言い切れません。
だからこそ仕事の需要がなくなっていくかもしれないというリスクと向き合うことも大切なんですね。
マークアップエンジニアの将来性を脅かす要因としては、以下のような理由が考えられます。
- 技術の進歩によるコーディングの自動化
- Webコーダーやマークアップエンジニアの増加による需要の低下
コーディングの自動化に関しては、マークアップエンジニアに限らずほとんどのITエンジニアが考慮すべき不安要素ですよね。
また、同業者が増えれば独自性や自分自身に付加価値をつける必要があります。
マークアップエンジニアの将来性を高めていくのに大切なのは、周辺の業務にも参画していくことでしょう。
周辺の業務とは、フロントエンドのマークアップ部分を担当するなどサイト制作以外の作業のことです。
また、他の職種へのキャリアアップも選択肢の1つになります。
マークアップエンジニアのキャリアパスについては以下で詳しく紹介していきますね。
マークアップエンジニアのキャリアパス
マークアップエンジニアの業務も網羅できる職種として、フロントエンドエンジニアだと知っている方は多いでしょう。
ただ、フロントエンドエンジニアにはどんなスキルが必要なのかや他のキャリアパスも確認しておきたいですよね。
そもそもキャリアパスには、キャリアアップという意味も含んでいます。
現状の職種より知識やスキルが必要になることは前提に置いておきましょう。
マークアップエンジニアのキャリアパスとしては、
- Webデザイナー
- Webディレクタ
- フロントエンドエンジニア
などが挙げられます。
それぞれのキャリアパスに必要なスキルや職種の特徴など、詳しく紹介していきますね。
Webデザイナー
1つ目のキャリアパスは、Webデザイナーです。その名の通り、Webサイトのデザインを考える職種で、クライアントの要望に沿ったデザインを提案します。
マークアップエンジニアと同じく、HTMLなどの言語知識を必要としますが、それ以外にもWebデザイナーになるには、いくつかの知識が必要です。
例えば、UI・UXを意識したデザインの知識が挙げられます。
UI(User Interface)はユーザーとデバイスの「接点」を意味しており、Web開発においては画面上に表示されているWebサイトそのものです。
Webデザイナーは、さまざまなユーザーに対して使いやすいレイアウトを構築するためのデザイン力(UIデザイン)が求められます。
一方、UX(User eXperience)はユーザーの「経験」を意味し、Webサイトの利用を通して「ユーザーがどのように感じたか」に注目するのがポイント。
Webデザイナーは、単にWebサイトを作るのではなく、Webサイトの利用を通してユーザーが感じることを基にして、レイアウトを構築するためのデザイン力(UXデザイン)も求められます。
ほかにもWebデザイナーは、PhotoshopやIllustratorなどの画像編集・加工ソフトを頻繁に用いるため、これらソフトウェアが使いこなせることが前提です。
Webディレクター
2つ目のキャリアパスは、Webディレクターです。ディレクターは「監督」「指導者」といった意味を持ち、Webサイト制作の陣頭指揮をとるのが主な仕事。
マークアップエンジニアやWebデザイナー、そのほかWebサイト制作に関わるメンバーの管理や予算・品質の管理などを行います。
マークアップエンジニアと同様に、Web開発の知識が求められることはもちろん、ディレクター特有のスキルも必要です。
例えば、広告媒体としてのWebサイトを制作する場合は、より多くのユーザーを集客するため、マーケティングの知識が求められます。
また、クライアントの要望を正確に聞き出して最適なものを提案するため、コミュニケーションスキルやプレゼンテーションスキルも必要です。
フロントエンドエンジニア
キャリアパスの中でも、おすすめしたいのがフロントエンドエンジニアです。
なぜなら、フロントエンドエンジニアの仕事は幅広く、肩書きにとらわれずさまざまな仕事や案件に関わることができるからなんですね。
しかし、フロントエンドエンジニアに必要とされるスキルは多いのも事実です。
決して簡単な道のりではないですが、その先のキャリアパスまで見込むと目指す価値はあります。
フロントエンドエンジニアになるには、マークアップエンジニアのスキルにプラスして、
- gitなどのバージョン管理ツールに関する知識
- ReactなどJavaScriptのフレームワークを用いて、webアプリを制作可能
- PHPやMySQLに関する知識やスキル
など上記の知識やスキルが必要になります。
プログラミング言語への関わりが浅かったマークアップエンジニアの方の中には、難しそうと感じる方もいるでしょう。
ただ、会社や企業がWebマーケティングに特化しているなどの場合は、フロントエンドエンジニアに求められるスキルのハードルが低いこともあります。
あなたが進もうとしているキャリアパスに、必要な知識やスキルを事前にチェックして身につけていってくださいね。
マークアップエンジニアに未経験からなる5STEP
ここまで読んだ人はマークアップエンジニアのいい部分も悪い部分もわかったでしょう。
しかし、「未経験からマークアップエンジニアになるには何をしたらいいの?」と思っている人もいます。
次は、未経験からマークアップエンジニアになる方法を5STEPで紹介します。
5つのSTEPは以下になります。
- STEP1:VSCodeやWebアプリの仕組みを知る
- STEP2:JavaScript・jQueryを学ぶ
- STEP3:転職エージェントに登録する
- STEP4:復習する
- STEP5:GitHubに登録してコードを作り公開する
それぞれ詳しく解説しますね。
STEP1:VSCodeやWebの仕組みを知る
まず、VSCodeやWebの仕組みについて知りましょう。
VSCodeとは、マイクロソフト社が無料で提供しているプログラミング編集ソフトです。
仕組みについて知るにはVSCodeでHTMLやCSSを使って実際にブラウザでどのように映るのか実践的に勉強します。
実際にプログラミングして、ブラウザで表示させてみましょう。
最初は失敗が多いと思いますが、『どうしてこうなるのか』や『正しく表示させる方法』と自分で解決する論理的思考も身に付きます。
また、時間がある時Webの仕組みを知っておきましょう。
自分が使っているプログラミング言語やWebサービスの仕組みをあらかじめ知っておくことで、プログラミング言語を少ない時間で習得しやすくなりますよ。
STEP2:JavaScript・jQueryを学ぶ
ある程度、VSCodeでHTMLやCSSが理解できたらJavaScript・jQueryを学びましょう。
よく聞くJavaScriptは、多くのWebサイトでHTMLとCSS+JavaScriptを組み合わせて使われています。
例えば、Twitterのホーム画面は随時、トレンドやニュースで最新の情報が入れ替わっていますよね。
これは、JavaScriptのおかげで最新情報が入れ替わっているのです。
JQueryは、そのJavaScriptの土台となるフレームワークです。フレームワークとは、プログラミング言語でよく使う機能をまとめたものですね。
一緒に覚えることで1からコーディングする必要がなくなるので、制作時間の短縮にも繋がるのでおすすめですよ。
STEP3:転職エージェントに登録する
3つ目は、転職エージェントに登録します。
転職サイトで求人探しから面接まで自分1人でやるのは、時間がかかりすぎますので転職エージェントに登録して、エージェントと協力しながら転職を成功させましょう。
また、未経験からマークアップエンジニアになるには、HTML・CSS・JavaScriptの勉強が欠かせません。
転職活動期間中は自分は勉強することだけに集中して、求人は転職エージェントに任せたほうが効率よく転職できます。
転職エージェントとの面談では、業界のトレンドも教えてもらいましょう。
業界のトレンドを理解することで、企業が欲しい人材がわかるので取得すべきスキルや知識がわかり、採用率がよくなりますよ。
STEP4:復習する
4つ目は復習をしましょう。
具体的にはSTEP1とSTEP2の部分です。何回も復習して知識を定着させましょう。
人は、何回も復習することで覚えることができます。
何回も復習することでコーディング作業が早くなりますよ。
また、慣れてきたらパソコンのF12キーでWebサイトのコードを見ながらコーディングしてみることも練習法としておすすめです。
困った時は、ネットで検索してみたり本を見たりすることでどんなコードで書かれているのか見ることもできます。
何回も復習して、早くコーディングできるようになると会社からも貴重な人材になりますよ。
STEP5:GitHubに登録してコードを作り公開する
最後は、GitHubに登録してコードを作り公開しましょう。
GitHubとは、自分で作った作品を保存や公開することができるサイトです。
近年転職の現場でもGitHubアカウントの提出を求められる会社が増えています。
実際にどんなものを今まで作ってきたのかを気にする会社が多くなっており、GitHubアカウントの提出が増えているのです。
また、作ったものは公開をしましょう。
公開することで会社が作品を見ることができます。
公開していないとアカウントに載らないので、作ったら公開しておくことを忘れないでくださいね。
GitHubで作った作品も採用基準に入っているので登録しましょう。
GitHubは自分で作ったコードを保存できるのも特徴ですが、他人が作ったコードもみることができるのも特徴です。
今まで知らなかったコードを見ることで新しい発見があったりするので、登録しておいて損することはありませんよ。
マークアップエンジニアに転職する3STEP
未経験でマークアップエンジニアになる方法はわかりました。
しかし、エンジニアからマークアップエンジニアになる方法はどんなSTEPを踏めばいいのか気になる人もいるでしょう。
エンジニアからマークアップエンジニアになるステップは3つです。
- STEP1:転職エージェントに登録する
- STEP2:GitHubに登録してコードをサイト上で公開する
- STEP3:活かせる経験や実績をまとめる
未経験からマークアップエンジニアになるよりSTEPは少ないのですが、転職を成功させるためにしっかり見ることをおすすめします。
STEP1:転職エージェントに登録する
まず、転職エージェントに登録しましょう。
前職がエンジニアだったとしても転職エージェントをおすすめする理由は、転職エージェントの方があなたの要望や希望に沿った転職先を紹介してくれるからです。
転職エージェントは、転職サイトに載っていない求人も多く扱っているのであなたの要望や希望に沿った求人を提供しやすいのですね。
また、業界のトレンドを知ることで、自分に足りていない知識やスキルを確認して、資格を取ることも可能です。
STEP2:GitHubに登録してコードをサイト上で公開する
GitHubに登録して、コードをサイト上で公開しましょう。
これは上記でも説明した通り、転職先の企業でもこれまでどんなものを作ってきたのか気になっているのですね。
どんなものを作ってきたのか知るためにGitHubアカウントの提出が求められる会社もあります。
今まで、Web制作をしたことがないエンジニアの人はHTML・CSS・JavaScriptを使って作品を作りましょう。
STEP3:活かせる経験や実績をまとめる
最後に転職して活かせる経験や実績をまとめておきましょう。
例えば、前職でエンジニアだった人でリーダー経験がある人は『リーダー経験』と書くことができます。実績があれば、スキルもまとめておくといいでしょう。
しかし、履歴書に書くときは『リーダー経験』と書くのではなく、リーダー経験を通して何ができるようになったのか詳しく書くことが大事です。
面接官はあなたが何ができるのか全く知りませんからね。もし、活かせる経験や実績をまとめたら転職エージェントと一緒に相談することもいいですよ。
まとめ
今回は、マークアップエンジニアについて徹底解説しました。
マークアップエンジニアはスマートフォンやタブレットのデバイスが普及した今、需要が増えている職業でした。具体的な仕事内容は
- コーディング作業
- バグの修正
- CMSの構築・設計
- SEO対策
など、多くの仕事内容がありましたね。
大変な仕事でもありますがユーザーの意見がもらえたり、自分のアイデアが入れられたりとやりがいがあるのも事実です。
マークアップエンジニアを目指そうか考えている人は、年収や資格を見て判断するといいですよ。