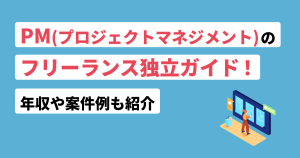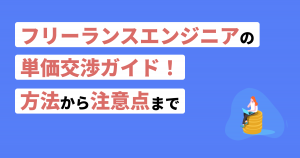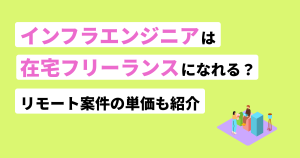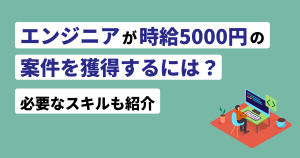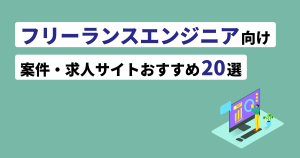「そもそも青色申告って何?」
「青色申告ってどうやって申告すればいいの?」
「いつまでに何の書類を出せばいいの?」
この記事に訪れたあなたはこのような悩みや疑問を抱えていませんか?
フリーランスとして活動するようになると自分で確定申告するようになります。
会社員だと会社側が税金を計算して給料を支払ってくれますから、確定申告をやったことが無い人が多く困っているのではないでしょうか。
さらに周りに頼れる人がいないと、自分で手続きを済ませるのも一苦労しますよね。
そこで今回は青色について紹介!青色申告のメリットやデメリット、やり方について解説していきます。
具体的な内容は以下の通りです。
- 青色申告や白色申告とは?
- フリーランスの青色申告のメリット・デメリット
- フリーランスで青色申告に向いてる人
- フリーランスの青色申告に必要な書類は?
- フリーランスの青色申告のやり方4STEP
- フリーランスエンジニアの青色申告によくあるQ&A
- 青色申告は「弥生の青色申告オンライン」を使って楽に提出しよう
この記事を読めば青色申告について理解出来て、悩むことなく確定申告の手続きが行えるようになりますよ。
青色申告と白色申告とは?
そもそも確定申告とは、あなたが1年間で稼いだ収入に対する税金を清算する手続きです。
源泉徴収だけでは不足する所得税を納めたり、逆に過払い分を返してもらったりするために行います。
そして確定申告には白色申告と青色申告の2種類があるのを知っていましたか?
- 白色申告とは?
- 青色申告とは?
ここではそれぞれの申告について解説していきますね。
白色申告とは
白色申告は簡単に言えば、手続きを簡易化した確定申告の方法です。事前に申請する必要もありません。
会社員で医療費控除の手続きをしたり、副業で収入があったりする人だと、白色申告の経験がある人もいるのではないでしょうか?
提出する書類は、収支内訳書と確定申告書Bを提出します。
期限は2月15日から3月15日までですが、期限を過ぎても提出できますよ。ただし延滞税などが発生してしまうので注意してくださいね。
青色申告とは
もう一つの確定申告の方法が青色申告です。
こちらは事前に申請が必要なものなので、会社員として働いている場合はたくさん資産があったり、副業の収入が多かったりしない限り使う場面は無いでしょう。
また青色申告は複式簿記を使用するため、簿記のスキルが求められます。
さらに期限を過ぎてしまうと青色申告ができなくなってしまうので、難易度がかなり高いと言えるでしょう。
こちらは個人事業主や法人を対象としたものであり、フリーランスの人だと節税の関係で青色申告を選択する人がほとんどになります。
フリーランスの青色申告のメリット・デメリット
青色申告は書類を作成するのがとても大変です。「青色申告はとても面倒だから、青色申告する必要はないんじゃないの?」と考える人もいるでしょう。
では事前申請の手間をかけてまで、青色申告を選ぶメリットはどんなものがあるのでしょうか?
青色申告のデメリットも合わせて解説していきますね。
3つのメリット
青色申告のメリットは3つ。やはりメリットは節税の部分が大きいです。
- 所得税の控除額が65万円に
- 赤字を繰り越せる
- 経費として計上できる金額が30万円に
上記の3つが青色申告にとってのメリットです。それぞれを具体例を交えながら詳細に解説していきますね。
所得税の控除額が65万円に
確定申告では特別控除と言って、所得の金額に関係なく引かれる控除が存在します。
例えば白色申告では10万円の特別控除があり、所得税がいくらであろうと変動せず10万円分が引かれるんですね。
一方、青色申告だと65万円まで控除されるんですよ。
具体例として経費や医療費などの控除を考えずに、年収300万円の白色申告時と青色申告時の所得税を比較してみましょう。
| 白申告をした場合 | 課税所得242万円×10%-特別控除97,500円=所得税144,500円 |
|---|---|
| 青色申告をした場合 | 課税所得187万円×10%-特別控除97,500円=所得税89,500円 |
手続きの方法が違うだけでこれだけの差が出ることがわかるでしょう。
控除額が55万円も増えるのはかなり大きなメリットなので、やはり青色申告を選ぶべきですね。
→参考:所得税の税率
赤字を繰り越せる
フリーランスとして軌道に乗っていない状況だと、収支が赤字になってしまうケースも少なくありません。しかし、青色申告では最大3年まで赤字を繰り越せるんですよ。
例えば過去3年間の収支が1年目・50万円の赤字、2年目・30万円の赤字、3年目・100万円の黒字だったとします。そこで、青色申告なら最大3年まで遡って赤字を繰り越せるので、3年目は1年目と2年目の赤字を繰越し、20万円の黒字として申告できるようになるんですね。
このシステムがない状態だと、3年目は100万円の黒字として申告するため、その分所得税も高額になってしまいます。
青色申告はそもそも控除額が大きいだけでなく、繰り越した赤字の分課税額を減らすこともできるので、青色申告の節税効果はかなり大きいことがわかるでしょう。
経費として計上できる減価償却資産の金額が30万円に
白色申告の場合、10万円以下の資産はまとめて申告できますが、10万円以上の減価償却資産は減価償却に基づいて経費として計上しなければいけません。
青色申告ではそのラインが10万円から30万円未満に引き上げられています。
減価償却資産とは、簡単に言えば「高価で長く使えるもの」のこと。仕事で使う高価なパソコンなどの機材は、安いものを購入するとすぐに壊れてしまうので、長く使うことを前提に良いものを購入しますよね。
そこで10万円以上の仕事に使う機材などの資産を減価償却資産と言い、所得税法などで定められた耐用年数分に分割して経費として計上します。
例えば20万円のパソコンを購入した場合、耐用年数は4年と定められています。減価償却の方法には毎年一定の金額を減価償却費として支払う定額法と、を用いて計算すると、毎年5万円ずつ4年間経費として計上していくこととなります。
フリーランスだと高額なパソコンなどを購入すれば10万円は軽く超えてしまうので、「いちいち減価償却していたら面倒…」だと思いますよね。
それに高額な機材を購入した年は大きな出費のせいで生活が苦しい人もいるでしょう。そのため、少しでもその年の経費を大きくして所得税を安く抑えたいたいところ。
そこで青色申告なら30万円まで減価償却をせずに経費として一度に計上できるので、その年の納税額を減らしてお金に余裕もできますよ。
3つのデメリット
節税の面でメリットが大きい青色申告ですが、手続きが面倒なのが難点。それでは、青色申告のデメリットを見ていきましょう。
- 確定申告が複雑
- 事前に申請書の提出が必要
- 期限に間に合わせないと控除が受けられない
上記の3つが青色申告にとってのデメリットです。それぞれを具体例を交えながら詳細に解説していきますね。
確定申告が複雑
青色申告では複式簿記の知識が求められます。簿記に触れたことがない人からすると、複式簿記に基づいた帳簿の作成作業は苦痛でしょう。
白色申告だと単式簿記と言って、青色申告よりもシンプルに帳簿が作れます。複式簿記は記入する欄が多く、帳簿の作成作業に時間もかかりやすいです。
ただ、近年だと確定申告の書類作成は確定申告ソフトを使うのが一般的。確定申告ソフトだと簿記の知識がなくても青色申告の手続きが簡単にできます。
日々の記帳作業も楽になるので、フリーランスとして独立する際は確定申告ソフトを導入するのがおすすめですよ。フリーランスにおすすめの確定申告ソフトについては後ほど解説しますね。
事前に申請書の提出が必要
先ほど解説したように、白色申告は何の申請もなしに確定申告ができますが、青色申告の場合、「所得税の青色申告承認申請書」という書類を事前に税務署に提出しなければいけません。
ちなみにこの書類は一度提出すれば、毎年更新などの手続きは必要ありません。一度きりなので負担にはなりませんが、申請書の提出を後回しにしていて気づいたら確定申告の時期だったということもあるので要注意です。
また、後ほど紹介する開業届は開業から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内に税務署に提出しなければいけません。特に罰則はありませんが、青色申告の時期に確実に間に合わせるために、できるだけ早く提出しましょう。
期限に間に合わせないと控除が受けられない
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です。青色申告の場合、この期間内に申請を済ませないと、65万円の控除が受けられなくなってしまいます。ちなみに10万円の控除は期間に間に合わなくても利用可能。
とは言っても、この期間内に確定申告を済ませなかっただけで大きな損失になってしまいます。65万円の控除を受けるためにも、必ず期間内に確定申告を済ませましょう。
フリーランスで青色申告に向いてる人
やはり税金を低く抑えられるメリットが大きいので、すべてのフリーランスが青色申告をすべきといえるでしょう。
また青色申告だと給与所得は対象外になるので、会社員のような給料をもらって生活する人には利用できません。
個人事業者やフリーランスなどが貰う事業所得などが対象になるので、青色申告するメリットはあるでしょう。
できればただお金を稼ぐだけではなく、支払う金額を抑えてお金を浮かせたいですよね。青色申告ソフトもあるので、簿記の知識が無い人でも安心してできますよ。
フリーランスの青色申告に必要な書類は?
青色申告では、『所得税の青色申告承認申請書』と『開業届』の2つが必要になります。
事業開始から2か月以内もしくは2月15日~3月15日の間に手続きを済ませないとその年の確定申告で青色申告が利用できず、翌年度からとなってしまうので注意してください。
では2つの書類には何を記入すればいいのでしょうか?それぞれ詳しく確認していきましょう。
所得税の青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書はその名の通り青色申告を利用するために必要な申請書です。書式は税務署もしくは国税庁の公式ホームページで入手できます。
こちらは比較的シンプルで、記入する情報は以下の通り。
- 提出先・提出日
- 納税地・氏名・生年月日・職業・屋号
- 青色申告の開始年度
- 事業所の所在地
- 所得の種類
- 過去の青色申告承認の取消しや取りやめについて
- 相続により事業継承した場合
- 開業する日について
- 65万円控除を受けるか否か
- 青色申告の特別控除について
- 特記事項について
- 顧問税理士について
基本的には指示通りに書けば問題ありません。ただ、「青色申告の特別控除について」と「65万円控除を受けるか否か」については間違えると青色申告ができなかったり、65万円の控除が適用されなかったりするので、提出する前に入念に確認しましょう。
また、税務署が混雑している可能性を考えると、書式をダウンロードして、自宅で記入してから税務署へ向かうのがおすすめです。
開業届
フリーランスとして独立するにあたって手続きが大変なのが開業届です。開業届を出さなくてもフリーランスとして働くことはできますが、この手続をしていないと青色申告ができません。
また、補助金・助成金の手続きができないなど、お金の面で大きな損をしてしまうので必ず独立時は開業届を提出するようにしましょう。
開業届の書式も税務署もしくは国税庁のホームページにて手に入ります。こちらは記入する欄が多いので、待ち時間を減らすためにできえう限り自宅で記入しておくといいですよ。
開業届に記入するものは以下の通り。
- 提出先・提出日
- 氏名・生年月日・個人番号
- 納税地・住所
- 職業・屋号
- 届出の区分・所得の種類
- 事務所等を新設した日
- 開業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
特に書き直しの指導が入りやすいのが事業の概要です。ここに記入する情報が曖昧だと、再度書き直すように言われる可能性が高いので、できるだけ細かく事業内容を記載しましょう。
青色申告承認申請書提出時には開業届の控えが必要になります。そのため、控えは必ず取っておきましょう。
フリーランスの青色申告のやり方4STEP
確定申告をやったことのない人には「そもそも確定申告ってどうやるの?」と疑問に思ってしまうかもしれません。
そのように考えている人は以下の4STEPで確定申告できますよ。

それぞれ具体的な手順を解説していきますね。
STEP1:確定申告書を入手する
確定申告は税務署もしくは国税庁の公式ホームページで入手できます。
まずは上記のサイトにアクセスしましょう。次に『確定申告書、青色申告決算書、修士内訳書等』の項目にある○○年分の確定申告書等にアクセスします。
書類の一覧が表示されますので『収支内訳書・青色申告決算書等』にある『所得税青色申告決算書(一般用)』をダウンロードか印刷すれば使えますよ。
ちなみに開業届は以下のサイトからダウンロードできますので、必要な方はこちらも入手しておきましょう。
STEP2:確定申告書に必要事項を記入する
必要種類を入手できましたら、記入する前の準備として、日々の領収書や収入がわかる書類を印刷してまとめます。
確定申告で最も面倒と言われる段階であり、1年分の領収書を記帳しないといけません。
確定申告シーズンにまとめて一気に起業しようとすると、漏れが出たり作業量が多くて挫折しかけたりしてしまいまうんですね。
そのため1週間~1か月に1回ペースでまとめて行うようにしましょう。
領収書などをまとめて、収入や経費などを把握できたら、それを確定申告書に記入します。必要事項は基本指示通りに記入すれば問題ありません。
また、確定申告書はe-taxで入力するのがおすすめですよ。
どこに何を記入すれば良いかなどがわかりやすいですし、間違いがあった場合は税務署の担当者が教えてくれるんですね。
確定申告初心者の人でも安心して記入できますよ。
STEP3:確定申告書を税務署に提出する
確定申告書の準備ができたら税務署に提出となります。
e-taxで確定申告書を作成した場合、そのままe-tax経由で提出できますが、税務に関する知識がなくて不安なら、紙に印刷して税務署に持っていくのが無難です。
STEP4:所得税を納める
確定申告書を提出し、所得税の申告が済んだら、申告した分の所得税を納めることとなります。
ちなみに税務署の窓口でも支払いができるので、できるなら確定申告をした際に、そのまま税務署で納税するのがおすすめですよ。
フリーランスエンジニアの青色申告によくあるQ&A
基本確定申告には、事業のために使ったお金関係を記述します。しかし中には「これってどうなの?」と疑問に思う部分があるのではないでしょうか?
ここでは青色申告するうえでよく疑問に感じる3つのQ&Aを紹介します。

それぞれ具体的な回答を載せながら解説しますね。
疑問点1:100万円稼いでも青色申告で所得税はかからなくなる?
多くのフリーランスが抱える疑問点として、「今年は100万円しか稼げなかったけど、青色申告したら、所得税はなくなるの?」というものがあります。
青色申告をした場合、まず基礎控除として48万円が所得から引かれ、さらに青色申告の特別控除65万円が所得から引かれました。
そのため所得税が113万円までならば、課税所得が0円になるため、所得税は発生しなくなりそうですよね。
結論を言うと、上記の内容は正しいです。つまり1年で100万稼いだ場合は青色申告すると所得税が発生しなくなるんですね。
疑問点2:ICカードをチャージした時の費用はどうするの?
普段私たちは交通系ICカードを利用して電車に乗ったり買い物をしたりしています。
そこで交通系ICカードに関して「ICカードにチャージした時の費用はどうしたらいいんだろう…」と考えている人もいるではないでしょうか?
公用で利用しているICカードの場合、チャージした時点で前払費用に計上します。そして利用した金額分を費用に計上して、前払費用を取り除けばいいんですね。
私用と公用を同じICカードで利用している場合は、それぞれ分けて所持すると計算がしやすくなりますよ。
ちなみにICカードはチャージ専用機や自動券売機などで領収書を発行できるので、覚えておくといいでしょう。
疑問点3:車が全損して車両保険が降りた場合はどうするの?
フリーランスとして生活していると、想像していなかった事態が起こる場合もあります。
例として、事業用の車が全損して車両保険が満額出た場合はどうなるのでしょうか?
保険金が下りた場合、保険金収入の消費税は国税庁によると、損害賠償または保険金として受け取ったものについては原則非課税になります。
つまり所得税の計算上では一切関係ありません。
また非課税は所得税とは無関係なので、帳簿に記入する必要もありませんよ。
青色申告は「弥生の青色申告オンライン」を使って楽に提出しよう

ここまで読まれてきた方の中には、「青色申告は書類の準備が大変そう…」と思われた方もいるはず。
そのように感じた方は青色申告の手続きを楽にしてくれる『弥生の青色申告オンライン』を利用しましょう。
弥生は簿記の知識が無くても簡単に青色申告ができるのが強みです。
また会計ソフトの中でも歴史が長いので、昔から会計ソフトを使っている方からすると信頼度が高いソフトと言えるでしょう。
初年度は無料で利用できるのも魅力的。2年目以降も8,000円/年~のセルフプランと他の会計ソフトと比べても料金がかなり低いんですよね。
ただしサポートが欲しい場合は12,000円/年~のベーシックプラン、20,000円/年~のトータルプランと少し高い料金になってしまいます。
ですがサポートが要らない人にとっては少ない料金で楽に青色申告ができるのでおすすめのソフトといえますね。
まとめ
今回はフリーランスの青色申告について解説してきました。
青色申告は通常の確定申告と違って控除金額が大きかったり所得税を減らしたりできるので、フリーランスにとっては青色申告を選択すべきでしょう。
その反面、事前に承認しなくてはならない、1年分の領収書が必要になる、提出後に修正してもらう場合があるなどの面倒な手続きもあります。
そのため青色申告をスムーズに終えられる会計ソフトを利用して、確定申告に臨みましょう。
これからフリーランスになる方は、こういった確定申告をする必要があるということを頭に入れてくださいね。